
バイオサイエンスの魅力に取りつかれて
「分子消化器病」第5巻2号 90ページ 2008年「私の研究履歴書」より
1972年、東京大学理学部を卒業後、東大医科学研究所、チューリッヒ大学分子生物学研究所、東大医科学研究所、大阪バイオサイエンス研究所、阪大医学部、京大医学部と日本の研究者にはあまり見られないほど、職場を変えてきた。その間、研究テーマは蛋白質の生合成に関与するペプチド鎖延長因子(elongation factor、EF-1) の生化学から、分子生物学的手法を取り入れたインターフェロン(IFN) や 顆粒球コロニー刺激因子(G-CSF)の解析、そして、細胞死、死細胞の貪食過程の解析へと変遷してきた。本稿では、サイエンスの魅力に取り憑かれた35年間を振り返る。
1. 大学院----医科学研究所・上代研究室
私が育った金沢市は、タカジアスターゼやアドレナリンの発見者であり三共製薬の創始者である高峰譲吉博士の生誕の地です。高峰博士は郷土の偉人として小学校、中学校で取り上げられ、子供の頃から「科学者」に淡い憧れがありました。実際、生物学に興味を持ったのは、1968年、東京大学に入学し、教養学部で丸山工作先生から、生物学の講義、ゼミを受けたときです。丸山先生はワトソンの「遺伝子の分子生物学:Molecular Biology of the gene」を教科書に、生物を遺伝子や蛋白質、分子の言葉で理解しようとする考え方を教えていただきました。専門課程では理学部の生物化学科に進学しました。名古屋大学の岡崎怜治先生のDNA複製に関する集中講義で、Okazaki fragment 発見の話であり、講義の後すぐ図書室で彼の論文[1]をコピーしました。
それをきっかけに生物学に興味を持ち、沢山の本を読みました。生化学よりさらに進んだ「量子生物学」などの教科書を読み、理学部の卒業実験では宮澤辰雄先生の研究室で、赤外線によるペプチドの構造解析を行いました。しかし、大学院の研究室を選ぶとき、より生物に近いことがふさわしいと思い、医科学研究所の上代淑人先生(現・京都大学)に修士の学生として受け入れてもらえるようお願いしました。上代先生、「研究室は一杯で、新たに受け入れる余裕は無い。」とのことでしたが、当時、上代研究室に所属していた岩崎健太郎先生が小生の出身高校をみて、「この学生は私の高校の後輩である。」の言葉で上代研究室に拾ってもらうことになりました。確かに研究室は一杯で、実験机が無く、流しに板のふたをして、その上で実験をしていました。
上代先生の研究室には医学部、理学部、農学部の学生が混在していて,非常に個性のある人たちの集まりでした(図1)。上代先生、「この研究室はOtto MeyerhofからSevero Ochoa につながる世界の生化学の伝統を引き継ぐ研究室である。」とのべられ、研究室は世界に認められるサイエンスをめざしていました。月曜朝行われるJournal Clubで医学に関連する論文紹介が多く、医学的発想を教えてもらえる環境は大変有意義でした。私の修士課程のテーマはリボソーム上でペプチド鎖の延長反応を触媒する因子(Elongation Factor、EF-1)をブタの肝臓から精製しその酵素科学的な解析をすることでした。

図1.1975年当時の東京大学医化学研究所・上代研究室。後列右から4番目が上代淑人教授、前列右から3番目が岩崎憲太郎助教授、前列左から2番目長田。他に新井賢一夫妻、渋谷正史氏、宮島篤氏、水元清久氏など
アメリカの研究室から発表された論文があるからこれを追試するようにとのことでした。ところがこれが上手くいかない。めげずに実験をしていると、肝臓からの抽出液を硫安分画して透析すると、90%以上の活性が失活することがわかりました。そこで、これを安定化する方法を見つけて精製すると,これまで論文に書かれていたものとは分子量や性質が全く違うもの、EF-1としての機能によりふさわしい分子が同定できました[2]。何カ月も苦労していた問題がある日突然、解決される。その瞬間は本当にすごい感動でした。EF-1の酵素活性を測定するにはアイソトープで標識されたアミノ酸が蛋白質に取り込まれたかどうか測定します。医化学研究所の地下にアイソトープ室があり、夜中、液体シンチレーションカウンターの前で踊っていました。修士2年の頃です。この思いが忘れられなくて,やみつきになってしまいました。
最近、大学院改革の名前で大学の講座制が槍玉にあがり、大きなクラスでの授業、実習が奨励されています。私はこのような体制で科学者は育たないと思います。上代先生の「ピペットの持ち方から教えてあげます」との言葉通り、上代先生、岩崎先生から実験の進め方、実験ノートの書き方など非常に丁寧に文字通り“man to man”の形で教えていただきました。上代研究室で毎日行われる先生や先輩との討論、Journal Club, Progress Reportなどのmeetings、これらで鍛えられました。最初のテーマでぶつかった論文の追試ができなかったことも、発表された論文に対する教訓になりました。よい指導者の下で徒弟奉公することでしか、科学者としての訓練、修練はできないと思っています。
2.留学、ワイスマン博士、インターフェロン
私が大学院の学生であった頃は、遺伝子工学が始まろうとしていた時期です。1975-1976年、米国のManiatisらがウサギ・グロビンの mRNAから cDNAを作成し、これをベクターに組み込み、大腸菌で増殖させたと発表しました[3, 4]。この論文は私にとって大きな転機になりました。この技術、組換え DNA技術を習いたいと思いましたが,当時の日本ではどの研究室でもやっていません。危険な技術だと思われていて,世界的にも限られた場所でしか行われていませんでした。そこで、上代先生に相談したところ,New York 大学,Ochoaの研究室で上代先生と同僚だったチューリッヒ大学の Weissmann先生を紹介して下さいました。Weissmann先生は、バクテリアファージの研究をされていて,組換え DNA技術も進められているとのことで、1977年秋、留学することになりました。
Weissmann先生の研究室では,これまで日本では使ったことの無いdisposableの製品(Eppendorf tube, disposable pipette, tissue culture dish)がふんだんに用いられ,信じられないことばかりでした。まずはQbファージに人工的に変異を導入する実験から始めました。研究室では谷口維紹氏(現東京大学医学部教授)がおられ、実験の手技など教えてもらいました。Weissmann先生は8時過ぎに研究室に現れて毎日「What’s new?」と聞いて回ります。何らかの新しいデータを用意しておかなければなりません。その圧力は強いものでしたが、彼とのDiscussionは楽しく、大変勉強になりました。
1978年からヒトのインターフェロン(IFN)の cDNAを単離する研究を始めました。最初は谷口維紹氏がこのプロジェクトを担当しましたが、彼が1978年年末帰国することになり、私が担当することになりました。(谷口維紹氏は日本の癌研究所でIFN cDNAのクローニングを続けられました。)センダイウイルスを感染させたヒト白血球からcDNAライブラリを作成し、その2万個のクローンの中からIFN cDNAを探し出すことになります。25年も前、IFNのアミノ酸配列が決まっていない時期であり、発現クローニング法もありません。2万個のクローンを100個づつ200個のプールにわけ、そのplasmid DNAにIFN 産生細胞から調製したmRNAをハイブリダイズ、ハイブリダイズしたmRNAをアフリカツメガエルの卵母細胞に注射、それを2日間培養した後、その培養液中にIFNがあるかどうかバイオアッセイする。結果が出るまでに10日かかる気の遠くなるような作業です。IFNは非常に量が少なくて何万個のクローンの中に1つ位しかないと思われていました.しかしアッセイを繰り返していくうちに,100個に1個くらいのクローンが陽性になりました。Weissmann先生は「一体これは何だ。Assayが全く動いていないではないか」と怒りましたが,こちらはそんなことは考えられない,と反論しました。すると、Weissmann 先生「君が陽性と思う大腸菌の溶解物に IFN活性があるかどうかを調べてみろ」と言い出しました。そこで大腸菌から抽出液を調製、調べてみたところ,なんとIFNの活性が見つかったのです。大腸菌がヒトの IFNを作っていたのです。1979年12月24日、研究室には一緒に仕事をしていた平秀晴氏(現岩手大学教授)、ボストンからSummer studentととして研究室に来ていたMichel Streuliの3人だけ、抱き合いました。Weissmann先生はクリスマス休暇でスキーに行っていましたが,その日の正午に研究室に電話があり、「大腸菌が IFNをつくっている」という私の言葉を聞くと「Fantastic!」と一言。3時間後にはアルプスから研究室に戻ってきていました。それから、一週間、大腸菌で発現されているたんぱく質が実際にIFNであることを確認し、1980年の1月3日 Weissmann先生はマイアミでのconferenceに向かわれました。そして、スイスへの帰国の途中、急遽、1月16日ボストンでIFN 遺伝子単離に関する講演、記者会見をされました。その内容は次の日の New York Timesの1面に紹介されました。1月17日に Weissmann先生が研究室に戻ってきた時には,すでに投稿すべき論文がほぼ書き上がっていました。タイプライター(当時、ワープロはない)を購入し、空港の待合室などで書かれたたそうです。Weissmann先生はこの論文をイギリスNatureの編集部に持参、数週間後レフリーから「この論文はNatureのfront sectionに発表すべき論文である。」との、とてもうれしい、これまでの苦労が一掃されるコメントをもらい、3月27日号のNatureに掲載されました[5]。

図2.Time Magazine のインターフェロン特集号。1980年3月31日付けTimeの表紙。
IFNには抗癌作用が存在すると報告されていたことから,マスコミに大きく取り上げられました(図2)。何千もの患者さんから「分けてほしい」という手紙や電話でのリクエストが飛び込んできました.Weissmann先生はこれらに対して,「今はそういう時期ではない。これが薬として使えるようになるまでに何年もかかる」ということを丁寧に説明して返信されました。バイオサイエンスはインパクトが非常に強くて大変面白い分野ですが,それと同時にその成果の発表にあたっては、注意をしないと世間の人達を騙す結果にもなるのだと,強く思いました。ワイスマン研究室ではその後2年間に、大腸菌を使ってIFNの大量生産に成功、これを精製、サルを使った実験をし,最終的に臨床試験にまで発展していきました。

図3.Charles Weissmann 博士
臨床試験のため、IFNを研究室から搬送しようとした前の晩,Weissmann先生は私に「明日の朝まで自分がここに倒れていたら,搬送を止めろ」と告げた後、IFNを自らに注射されました。彼の自信と責任感に圧倒されました。このような先生(図3)の研究室で4年間過ごせたということはすばらしい経験であり幸運だったと思います。
3.帰国、東京大学医化学研究所、G-CSF
1982年1月, 医科研・上代研究室の助手として帰国し、研究室を分子生物学、遺伝子工学の研究室のset up にかかりました。そして、大学教官の義務として入学試験の試験監督に行った駒場の監督詰め所で当時医科研の講師だった浅野茂隆先生(現・早稲田大学)と一緒になりました。私がスイスでIFNのクローニングし、最近帰国したと話したところ,浅野先生がコロニー刺激因子について話し出したのです。「ヌードマウスにヒトの癌細胞を植え継いだら,マウスの白血球が非常に増えた。」浅野先生は癌細胞が白血球を増やす因子(CSF)をつくっているのではないかと考えていて,この因子に関して、浅野先生と共同研究を始めることになりました。帰国した当時に思ったのは,欧米のグループに簡単に勝てるものではないということでした。Weissmann研では全てのことがうまく組織化されていましたが,当時、日本では全て手作業。サイエンスのやり方が全然違うのです。日本の環境で世界に勝つためにはよほどの利点がないと難しい。浅野先生との共同研究に,この利点を感じたのです。浅野先生はCSFを産生するヒトのがん細胞を持っている。この癌細胞から私がcDNAを作成して発現クローニングを行う。次いで,浅野先生がヒト骨髄細胞を使ってCSFのアッセイをする。簡単そうに思えました。しかし、なかなかうまくいきません。スイスで簡単にいっていたことが動かないのです。また、お金もありません。1982年の秋、京都での国際会議の懇親会で、京都大学の中西重忠先生に愚痴りました。「お金も無い。何も無い日本でサイエンスはできない。ヨーロッパに戻る」。中西先生、烈火のごとく怒り出しました。「甘えるな。最近の君はくだらない日本語の総説、IFNに関して、雑誌をかえて次々、書いているだけではないか。そんな時間があれば仕事しろ。IFNはお前の仕事じゃない。ワイスマン博士の仕事だ。IFNは忘れろ!」。それから、2年、必死の思いで仕事をしました。中外製薬との共同研究という幸運にもめぐり合い、中外製薬から研究員を派遣してもらいました。そして、1985年G-CSFのcDNAを単離することに成功しました[6]。あの時、中西先生にどやされることがなかったら、どうなっていたのでしょう。
その頃、東京都臨床医学総合研究所に在籍していた米原伸さん(現・京都大学)と IFNの共同研究も行いました。IFNの働きを調べるために、IFNレセプターに対するモノクローナル抗体が必要だと米原さんは考えて,そのスクリーニングをはじめました。ヒトの細胞を抗原として、マウスを免疫、ハイブリドーマのライブラリーを作成します。そして、IFNレセプターに対する抗体をスクリーニングする。その抗体の存在では、IFNが作用せずにウイルスが細胞を殺すだろうというアッセイを行ったのです。その結果,1つのモノクローナル抗体の存在下で細胞が死滅しました。IFNもウイルスも関係なく,抗体だけで細胞が死んだのです。米原さんは、この抗体によって認識される抗原たんぱく質を Fasと命名した。
4.大阪バイオサイエンス研究所、Fas,アポトーシス
1985年、当時、大阪医科大学の学長をされていた早石修先生が突然、東京大学医科学研究所に訪ねてこられました。早石先生、「大阪・吹田に新しい基礎研究所を設立することを考えている。その研究所に加わらないか」と、話し始められました。それまで早石先生との面識はありませんでしたが、先生のサイエンスに対する熱意に感動し、どのような立場で参加するのかも確認せず、「私のようなものでよければ」と答えました。実際は、研究員やpost-doctoral fellow, 技術員を含めて10人近くのメンバーを引きいる研究部の部長としての職でした(図4)。いまだに何故、早石先生が私をこのような立場の職に誘ってくださったのかわかりません。

図4.大阪バイオサイエンス研究所第一研究部のメンバー。1987年4月。
1987年、私は大阪バイオサイエンス研究所に移りました。早石先生、「君の自由に仕事を進めればよい」とのことで,米原さんと Fas抗原を同定する仕事を始めたのです。苦労したのですが、アメリカDNAX研究所から帰国した伊藤直人君がExpression Cloning 法を導入し、Fas cDNAの単離に成功し,FasはTNF受容体ファミリーのメンバーであることを示すことができました。そこで、本来Fasを発現していない細胞にこのcDNAを導入し、Fas抗体を作用させると、細胞は速やかに死滅しました。生体の機能を保つために,細胞はあらかじめプログラムされた死を迎えるという“アポトーシス(apoptosis)”は,1972年に Kerrと Wyllieによって命名されていましたが、何がアポトーシスを誘導するか不明でした。Fasを刺激して細胞が死ぬ際に、アポトーシスのマーカーである DNAラダーが起こることを見つけ、Fasは細胞にアポトーシスのシグナルを伝達すると結論しました。これらの結果をCellに投稿したところ,1カ月ほどでコメントが返ってきて,「大変面白い論文だ。ただ,アポトーシスは電顕で確認すべきだ」との嬉しいコメントをもらい,追加実験を行い、1991年に論文が発表されました[7]。
その後数年間、次々と興奮することが起こりました。マウスのFas遺伝子を単離し、染色体上の場所を決めたところ、lpr (lymphoproliferation)という変異の近傍でした。Lpr マウスではリンパ球が異常増殖し,リンパ節や脾臓が肥大します。この細胞の異常増殖がアポトーシスの欠陥によるのではないかというna?ve ideaが浮かび、確かめたところ、実際、lprマウスの Fas遺伝子に変異が見つかったのです[8]。感激しました。ある分子の生理作用を調べるにはその分子に対する抗体の作成は必須です。私達、マウスFasに対するモノクローナル抗体を作成しました。ハイブリドーマが産生するモノクローナル抗体はその細胞をマウス腹腔に接種し、腹水から調製します。そこで、抗マウスFas抗体を産生するハイブリドーマをマウス腹腔に接種したところ、マウスは次の日までに、すべて死滅しました。一方、このハイブリドーマをin vitroで培養し、その培養上清より抗体を精製、マウス腹腔に投与したところ、このマウスも数時間以内に死滅しました。このことから、Fasの活性化によるアポトーシスは動物の個体に死をもたらす危険な過程との結論に達しました[9]。
FasはTNF受容体に類似した構造を持っており、これに結合するリガンドが存在するはずです。しかし、どのような細胞がFasリガンドを発現しているのかわかりません。Fasの細胞外領域にヒトのIgG コンスタント領域を結合させた分子を作成し、これに結合する分子を探し始めました。1年間ほどたった1992年12月14日、まだ、何の進展も無かったころです、マルセイユのPierre Golstein 博士から、Faxが届きました。「細胞傷害性T細胞のクローンを樹立した。このクローンは Fasを発現している胸腺細胞は殺すが、Fasに変異のある lprマウスからの細胞は殺さない。もしかしたら、この T-細胞クローンはFasのリガンドを用いて標的細胞にアポトーシスを引き起こしているのかもしれない。この細胞に興味があるなら送る」。もちろん,その日のうちに返信しました。
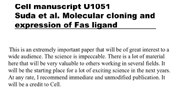
図5.1993年に発表したCellの論文に対するrefereeのコメント。
一週間後、細胞が大阪に届き、Fasリガンドの発現を確認、須田貴志君と高橋智之君が発現クローニング法でこの分子を単離、これがTNFaに類似した分子であることを示しました。細胞を送ってくれたGolstein博士とは1993年10月、Cold Spring Harborでのmeeting で初めてお会いしました。私がNew York に向かう直前にCellに送った論文[10]のコメント「This is an extremely important paper.----- At any rate, I recommend immediate and unmodified publication.」(図5)が大阪からNew Yorkに転送され,思わず、二人で握手しました。
5.大阪大学医学部・遺伝学、DNAの分解と死細胞の貪食
大阪バイオサイエンス研究所は研究をとてもやりやすい施設です。このような環境をより若い研究者に渡すべきだと考え、また、10年以上一箇所におれない私の性格などから、1996年大阪大学から誘いがあった際、移ることにしました。そこで始めた仕事がDNAの分解です。アポトーシス時には染色体DNAがヌクレオソームの単位(180bp)にまで切断されます。この現象はアポトーシス特異的に起こることから、アポトーシスのマーカーとも考えられ、数多くのグループがアポトーシス時に活性化されるDNA分解酵素の同定を試みていました。私達は、この切断がアポトーシス時に活性化されるカスペースの下流に存在すること、健康な細胞からの抽出液にカスペースを加えるとDNA分解酵素が活性化されることを見出しました。そして、そのことを指標にこのDNase(CAD, caspase-activated DNaseと命名)を精製、そのcDNAを単離しました。この酵素は核移行シグナルを持つDNaseで、合成された蛋白質がそのまま細胞質に遊離されると大変危険です。この酵素は単独では正常にfolding されません。CAD のinhibitor (ICAD, inhibitor of CAD)がそのfolding に必須でした。ICADはCADのnascent peptideに結合し、CADと1:1の複合体としてリボソームから遊離します。アポトーシスの刺激でカスペースが活性化されると、ICADが切断されCADから離れ、自由になったCADがDNAを分解する[11]。とても、巧妙な仕組みです。CADは2量体(homodimer)、はさみのような構造をもっており、その酵素の活性部位ははさみの最も奥に存在します。このため、ヌクレオソーム表面のDNAはこの活性部位に接触することができず、接触できるのはヌクレオソームをつなぐspacer領域のDNAだけ。CADの構造から、何故、アポトーシス時に染色体DNAがヌクレオソームの単位に切断されるか説明されました。このFasリガンドからCADへと導く一連のシグナル伝達は免疫の教科書「Immuno Biology」の表紙に取り上げられました(図6)。

図6.免疫学の教科書「Immuno Biology」第14版の表紙。FasリガンドがFasに結合、カスペースの活性化からCADによるDNA分解が模式化されている。
ついで、CADの生理作用を調べるためノックアウトマウスを作成しました。このマウスから調製した細胞にアポトーシスを誘導すると、どの細胞でもDNAの切断は起こらず、CADがアポトーシス時におこる染色体DNAの分解を担う唯一の酵素であることが確認できました。ところが、in vivoでアポトーシス細胞のDNA分解を調べると、どの組織でもDNA分解は正常に起こっていました。これはどういうことなのか。vitroの結果がvivoの結果と違っていたら,生化学、分子生物学の大前提が崩れます。なぜこんなおかしいことが起こるのかと組織を丁寧に観察し、生体内ではアポトーシス細胞はマクロファージに貪食され、死細胞のDNAはそのリソソームに存在するDNase IIによって分解されることをつきとめました[12]。そして、DNase II遺伝子を欠損させると、アポトーシス細胞や赤芽球からの核DNAが未分解のままマクロファージに蓄積し、これが種々の疾患を引き起こすことを見いだしました[13, 14]。また、この研究はそれでは、マクロファージはアポトーシス細胞の何を認識して貪食しているのだろうかの研究につながりました[15, 16]。
6.京都大学医学部、これから
サイエンスは一種の謎解き、ジグゾウパズルです。突き止めていけばいくほど面白くなります。わかっていると思っていることよりも,事実はもっともっと深い。実験をして予想もしなかったことが見つかったときの驚き、喜びは決して忘れられるものではありません。この分野は競争が激しい分野でもあります。しかし、よいcompetitionはよい友情をもたらします。IFN、G-CSF、Fasでそれぞれ、competitorであったDr. David Goeddel, Dr. Larry Souza, Dr. Peter Krammer とは、すばらしい友人です。
私は2007年5月、大阪大学から京都大学へ移りました。「Scientistの終息期に何故、また所属を変える」と多くの人達が怪訝に思われました。しかし、scientistに終息期はあるのでしょうか。私の最も尊敬する早石先生、90歳、いまだ現役です。先生は、Samuel Ullmanの「Youth」 をよく引用されます。「Youth is not a time of life; it is a state of mind; it is not a matter of rosy cheeks, red lips and supple knees; it is a matter of the will, a quality of the imagination, a vigor of the emotions; it is the freshness of the deep springs of life.」。私にとって、所属を変えることは、常に、新しい刺激、新しい発展をもたらしました。今回、もう一度そのチャンスが与えられたと思っています。若い学生さんとサイエンスを楽しもうと思います。
文献
1. Okazaki, R., Okazaki, T., Sakabe, K., Sugimoto, K., and Sugino, A. Mechanism of DNA chain growth. I. Possible discontinuity and unusual secondary structure of newly synthesized chains. Proc Natl Acad Sci USA 59, 598-605, 1968
2. Iwasaki, K., Nagata, S., Mizumoto, K., and Kaziro, Y. The purification of low molecular weight form of polypeptide elongation factor 1 from pig liver. J Biol Chem 249, 5008-5010, 1974
3. Efstratiadis, A., Maniatis, T., Kafatos, F.C., Jeffrey, A., and Vournakis, J.N. Full length and discrete partial reverse transcripts of globin and chorion mRNAs. Cell 4, 367-378, 1975
4. Maniatis, T., Kee, S.G., Efstratiadis, A., and Kafatos, F.C. Amplification and characterization of a beta-globin gene synthesized in vitro. Cell 8, 163-182, 1976
5. Nagata, S., Taira, H., Hall, A., Johnsrud, L., Streuli, M., Ecsodi, J., Boll, W., Cantell, K., and Weissmann, C. Synthesis in E. coli of a polypeptide with human leukocyte interferon activity. Nature 284, 316-320, 1980
6. Nagata, S., Tsuchiya, M., Asano, S., Kaziro, Y., Yamazaki, T., Yamamoto, O., Y Hirata, N.K., Oheda, M., Nomura, H., and Ono, M. Molecular cloning and expression of cDNA for human granulocyte colony-stimulating factor. Nature 319, 415-418, 1986
7. Itoh, N., Yonehara, S., Ishii, A., Yonehara, M., Mizushima, S., Sameshima, M., Hase, A., Seto, Y., and Nagata, S. The polypeptide encoded by the cDNA for human cell surface antigen Fas can mediate apoptosis. Cell 66, 233-243, 1991
8. Watanabe-Fukunaga, R., Brannan, C.I., Copeland, N.G., Jenkins, N.A., and Nagata, S. Lymphoproliferation disorder in mice explained by defects in Fas antigen that mediates apoptosis. Nature 356, 314-317, 1992
9. Ogasawara, J., Watanabe-Fukunaga, R., Adachi, M., Matsuzawa, A., Kasugai, T., Kitamura, Y., Itoh, N., Suda, T., and Nagata, S. Lethal effect of the anti-Fas antibody in mice. Nature 364, 806-809, 1993
10. Suda, T., Takahashi, T., Golstein, P., and Nagata, S. Molecular cloning and expression of the Fas ligand: a novel member of the tumor necrosis factor family. Cell 75, 1169-1178, 1993
11. Enari, M., Sakahira, H., Yokoyama, H., Okawa, H., Iwamatsu, A., and Nagata, S. A caspase-activated DNase that degrades DNA during apoptosis, and its inhibitor ICAD. Nature 391, 43-50, 1998
12. Kawane, K., Fukuyama, H., Yoshida, H., Nagase, H., Ohsawa, Y., Uchiyama, Y., Iida, T., Okada, K., and Nagata, S. Impaired thymic development in mouse embryos deficient in apoptotic DNA degradation. Nat. Immunol. 4, 138-144, 2003
13. Kawane, K., Fukuyama, H., Kondoh, G., Takeda, J., Ohsawa, Y., Uchiyama, Y., and Nagata, S. Requirement of DNase II for definitive erythropoiesis in the mouse fetal liver. Science 292, 1546-1549, 2001
14. Kawane, K., Ohtani, M., Miwa, K., Kizawa, T., Kanbara, Y., Yoshioka, Y., Yoshikawa, H., and Nagata, S. Chronic polyarthritis caused by mammalian DNA that escapes from degradation in macrophages. Nature 443, 998-1002, 2006
15. Hanayama, R., Tanaka, M., Miwa, K., Shinohara, A., Iwamatsu, A., and Nagata, S. Identification of a factor that links apoptotic cells to phagocytes. Nature 417, 182-187, 2002
16. Hanayama, R., and Nagata, S. Impaired involution of mammary glands in the absence of milk fat globule EGF factor 8. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 102, 16886-16891, 2005
